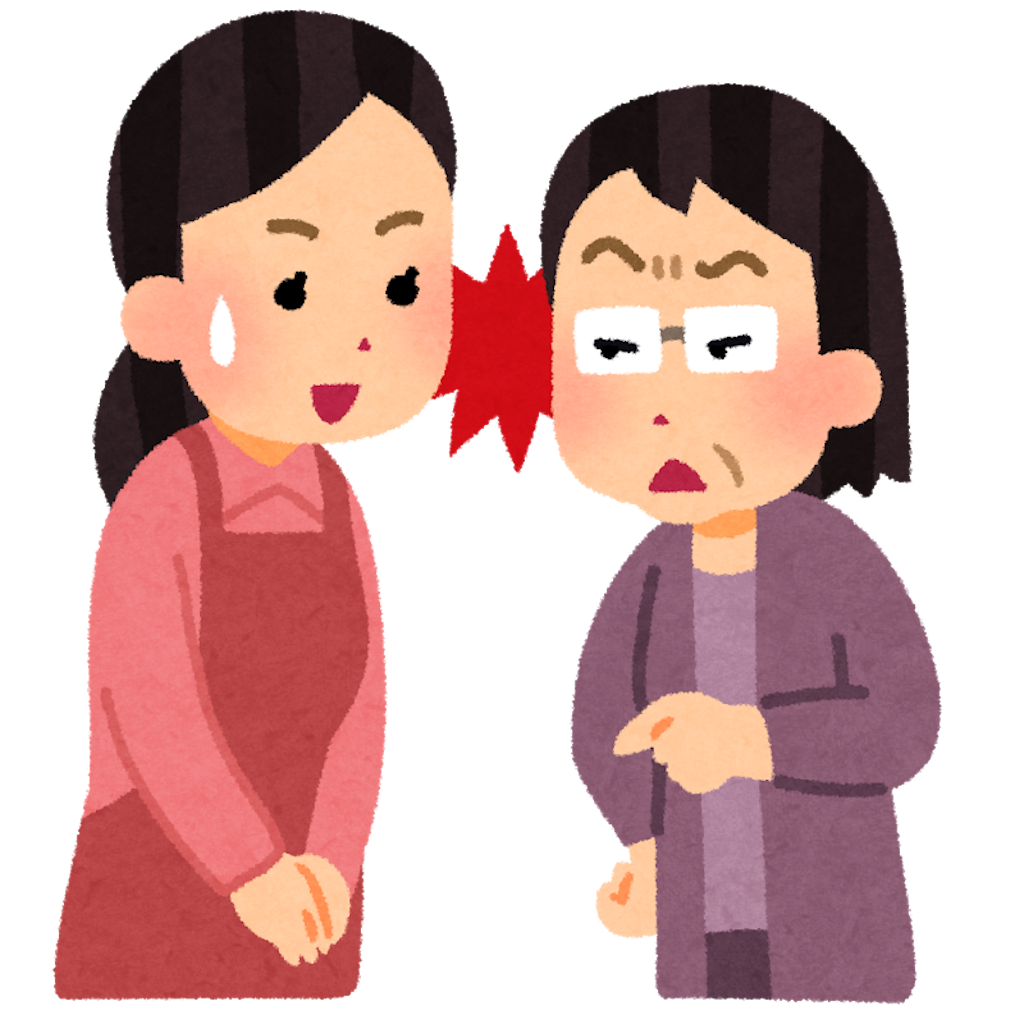
ドラマや映画の中に出てくる管理職は、口うるさく部下に指示を出しているシーンが多くないですか?実際、職場には小言が多い上司が多いのではありませんか?別に上司が意地悪なわけではなく、マネジメントの本質が口うるさくさせるのです。
マネジメントの目的とは
マネジメントの目的は多岐に渡りますが、ワンワードで表現しろと言われたら「機会損失をなくすこと」とお伝えします。ここ2回、マネジメントの歴史について紐解いてきましたが、製造現場であれ、営業現場であれ生産性を高めるためにマネジメントは誕生し、発展してきました。不良品を出さない、工場のラインを効率よく動かす、売り場で欠品による販売機会を逃さない。。。重箱の隅を突くように、細かいことに気を配るのはマネジメントの宿命のようなものです。だから職務に忠実な管理職ほど口うるさくなるのは仕方なかったりします。
スキルセットが変わる
マネジメントの目的は機会損失をなくすことと書きました。マネジメントの前提としてキャッシュを生み出すビジネスモデルが成り立っているということがあります。そのような前提があるから、「機会損失をなくす」というマネジメントの意義が存在します。
しかし、現在、多くの企業が求めているのはマネジメントではなくイノベーションだったりします。新しい価値を作りだす人材です。この点に経営者はジレンマを抱えます。マネジメントが得意な人とイノベーションが得意な人は異なります。両方を高いレベルでこなせる人材は希少価値が高い存在だからです。また多くの企業は既存ビジネスを抱えているため、そのビジネスを回すマネジメントできる人材も必要です。そのため評価や昇進のシステムはマネジメントができる人を育成し、評価するような仕組みになっています。社内で優秀であればあるほどイノベーション人材を輩出できないという矛盾が生まれるのです。
イノベーション人材は傍流から生まれる
どんな企業にも花形部署が存在します。そこで活躍した人材が出世していくというシステムです。しかし前述したように、マネジメントができる人とイノベーションを起こせる人は異なります。だから花形部署でキャリアを築いてきた人材は、ビジネスモデルが安泰な時はいいのですが、変革を行う際にはむしろマイナスの影響を与えかねません。
そんな事態を防ぐために、大企業は若くて優秀な人材を子会社へ出向させます。異質な経験を積ませ、そこで成功した人材を引き上げるのです。もっとも時の経営者が懐の深い人物でなければ、いくら子会社で業績を上げても抜擢されることはありませんが。その辺りは、時の運も大きく影響するようにも思います。ただ、多くの企業がイノベーションを求めているのは間違いないので、よりそれまで社内では傍流と呼ばれていた部署や、子会社で輝く人材にスポットライトがあたりやすくなってくるように思います。

ザ・ラストマン 日立グループのV字回復を導いた「やり抜く力」
- 作者: 川村隆
- 出版社/メーカー: KADOKAWA/角川書店
- 発売日: 2015/03/07
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (5件) を見る